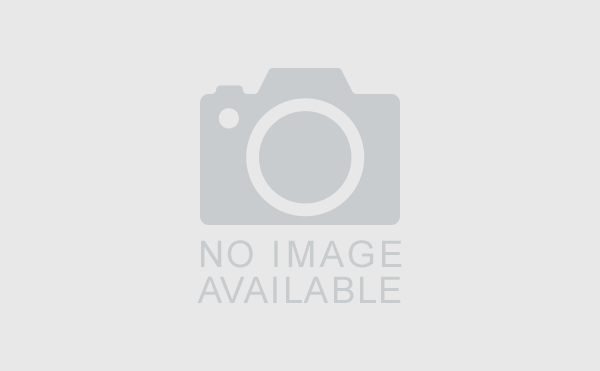新暦と旧暦の整理
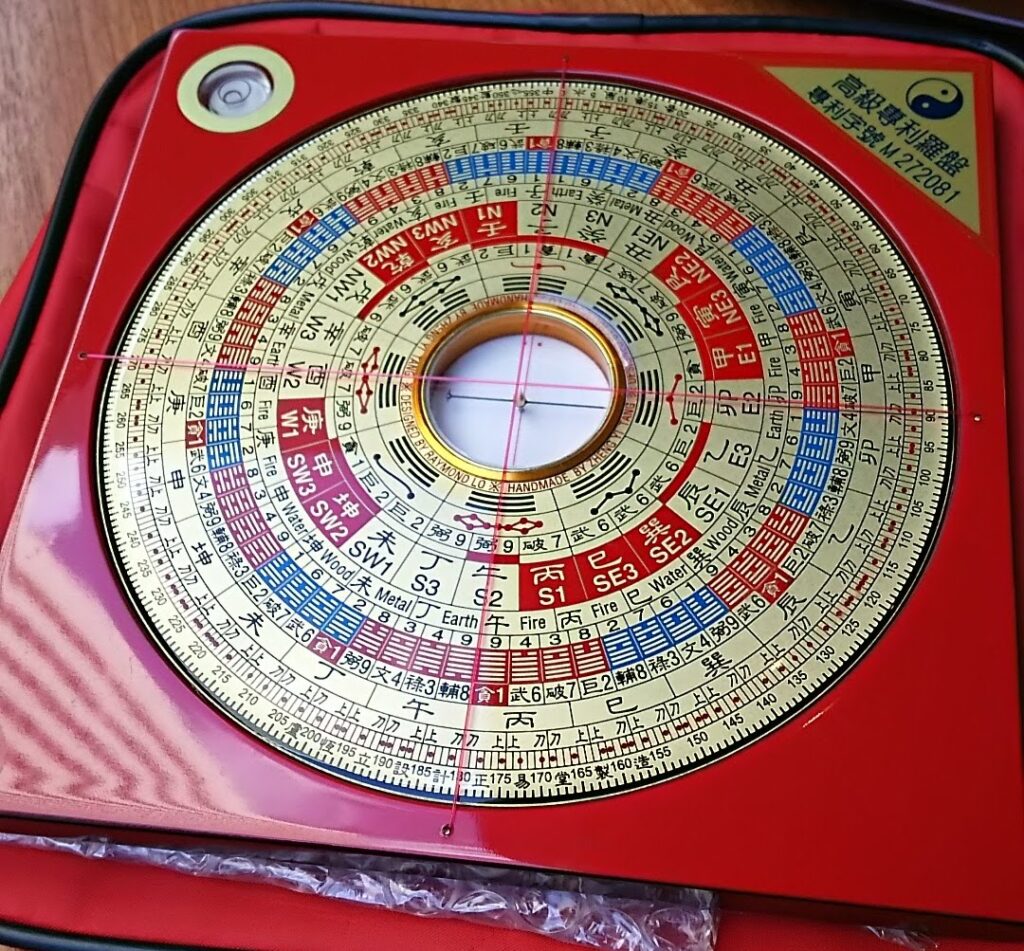
まずは、新暦と旧暦の整理から説明します。
今現在使っている暦を新暦(しんれき)。新暦に変わる前に使っていた暦を旧暦(きゅうれき)といいます。新暦・旧暦の具体的な暦というのは国ごとに異なります。日本では、新暦はグレゴリオ暦(太陽暦)、旧暦は天保暦(太陰太陽暦)です。明治5年12月2日の翌日(明治6年1月1日)をもって旧暦から新暦へ切り替わりました。
旧暦と新暦
・新暦/グレゴリオ暦(太陽暦)
太陽の運行を基準にした暦で1年は12か月です。
1年の始まりの1月1日に天文学的意味はありません。
・旧暦/天保暦(太陰太陽暦)
月の満ち欠けを基準にしつつ、太陽の動きも考慮した暦です。月の始まりは新月です。
3年に1度、うるう月があり、その年だけ1年が13か月となります。
1年の始まりの1月1日(旧正月)は、立春(新暦で2月4日頃)に最も近い新月の日です。
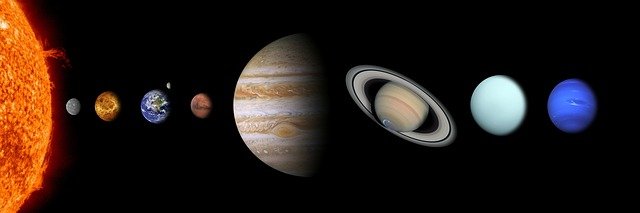
占いで使う暦とは何者か?
四柱推命や九星気学で普段使われる暦(俗にいう万年暦)とは一体何なのでしょうか。
1年の始まりは立春
古来より、冬至を基点として観測することで暦を正し、1年の始まりを冬至としていました。
中国の漢の時代、1年の始まりは立春へ変更されました。
のちに季節感を表す指標として二十四節気があらたに考案されました。
二十四節気(にじゅうしせっき)
二十四節気は、季節感を表す指標として暦に追記して使われます。もともとは太陰太陽暦に季節の変化を反映するために考え出されました。
二十四節気
1年の太陽の運行を24等分して、各々に季節を表す言葉を付けたもの。
年の始まりは立春(太陽暦の2月4日頃)とします。
各月の始まりも太陽暦では4日~7日ほどずれて始まります。
現代の暦と二十四節気
当初、暦や二十四節気は恒気法という方法によりつくられていました。
鎖国をしていた江戸時代中期、西洋から天文学が入ってきて、それをもとに定気法という新しい手法で暦を新しく作り変えました。それが天保暦です。その流れで、のちに二十四節気も定気法で創られるようになりました。
同じころ、中国においても定気法へ切り替えられました。
現在、世界的に使われているグレゴリオ暦と、主に日本で使われている二十四節気は、定気法によりつくられています。
そして占いの暦(万年暦)に利用されています。
万年暦
グレゴリオ暦に二十四節気を加え、干支を配当して四柱推命用の暦(干支暦)としたり、九星を配当して九星気学用の暦とします。
日本の中で発展する四柱推命と九星気学
中国本来の四柱推命は恒気法で作られた暦と二十四節気によって発展してきました。そのため、当時の中国の書物に書かれている四柱推命の理論は、恒気法のもとで成り立ちます。
恒気法で作った二十四節気と、定気法で作った二十四節気では、月の区切りが数日ずれることもあります。また、1年の区切りも異なります。そのため、同一の誕生でも命式の八字が変わってくる場合もありえます。
・・・
そのような背景がありつつも、
江戸時代中期に日本に四柱推命が入ってきました。
明治時代になると九星気学が生まれます。
定気法のもとで、どちらも日本の中で発展し続けています。