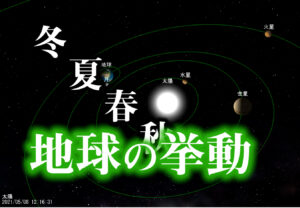四柱推命と暦のタイムライン

新暦、旧暦、二十四節気、恒気法、定気法、太陽暦、太陰太陽暦、冬至、春分、グレゴリオ暦、天保歴、。。。。etc.
色々ありすぎて、混乱した頭の中をすっきりさせるために、暦の歴史をまとめてみました。
注)青字で書いてある部分は中国に関する出来事になります
年~
中国の春秋戦国時代(しゅんじゅうせんごくじだい)
中国では、1年の始まりを冬至やその1ヵ月後や2ヵ月後にしていました
年~
中国の前漢(ぜんかん)の時代
中国では、1年の始まりを冬至から立春へ変更しました
ごろ~
6世紀から7世紀はじめごろ
中国の宋から元嘉暦(げんかれき)が伝来
具体的な使用開始年代がはっきりしません
ごろ~
飛鳥時代から奈良時代
中国の唐から儀鳳暦(ぎほうれき)が伝来
元嘉暦と併用していたが文武天皇元年(697)から本格的に使用開始
※文武天皇の即位について、日本書紀では元嘉暦で乙丑、続日本紀では儀鳳暦で甲子と書かれています
年~
天平宝字八年
吉備真備が中国の唐から持ち帰った大衍暦 (だいえんれき) を使用開始
年~
天安二年
中国の唐からが伝来した大衍暦 (だいえんれき) を使用開始
4年間だけ大衍暦と併用して使われた
年~
貞観四年
中国の唐から伝来した宣明暦 (せんみょうれき) を使用開始
この後、823年間使われた
年~
中国の明の時代(元の至元十八年)
中国では、授時暦 (じゅじれき)へ改暦しました
中国暦で最高峰といわれる
この後、364年間使われた
年~
中国の清の時代(順治二年)
中国では、時憲暦(じけんれき)へ改暦しました
中国で最後の太陰太陽暦法による暦
中国で定気法が初めて採用された暦
年~
翌貞享二年
貞享暦 (じょうきょうれき)として使用開始(貞享の改暦)
天文現象と実態が合わなくなってきて、江戸幕府のもとで改暦
天文暦学者の渋川春海 により、中国暦の授時暦(じゅじれき)を改良した暦
アップデートを繰り返して日本独自の暦を開発
年~
宝暦5年1月1日
宝暦暦(ほうりゃくれき)を使用開始
将軍徳川吉宗の命により、中国暦ベースから西洋天文学をベースに改暦を試みる
うまく行かず最終的に貞享暦をベースに若干改良
年~
明和8年
修正宝暦暦を使用開始
宝暦暦が不評だったため改良
年~
寛政十年
寛政暦 (かんせいれき) を使用開始
西洋天文学を採り入れた中国の暦書をもとに西洋天文学を取り入れた暦を完成
年~
天保15年1月1日
天保暦 (てんぽうれき) へ改暦
西洋天文学を西洋書から直接採り入れて暦を完成
日本で最後の太陰太陽暦による暦
日本で定気法が初めて採用された暦
のちに二十四節気も定気法によりつくられる
年~
明治6年1月1日(新暦)
グレゴリオ暦へ改暦
これが現在の暦
一般に新暦と呼ばれる
定気法によりつくられた太陽暦
二十四節気も定気法によりつくられている
1年の初めの1月1日に天文学的意味はない
年~
中華民国の成立(民国元年)
中国では、グレゴリオ暦へ改暦しました
辛亥革命(しんがいかくめい)を経て中国の清の時代が終わる
農暦という名称で太陰太陽暦が残る